愚痴ってもいいのか?──スポーツメンタルコーチが見つけた“言葉の力”と成長のヒント
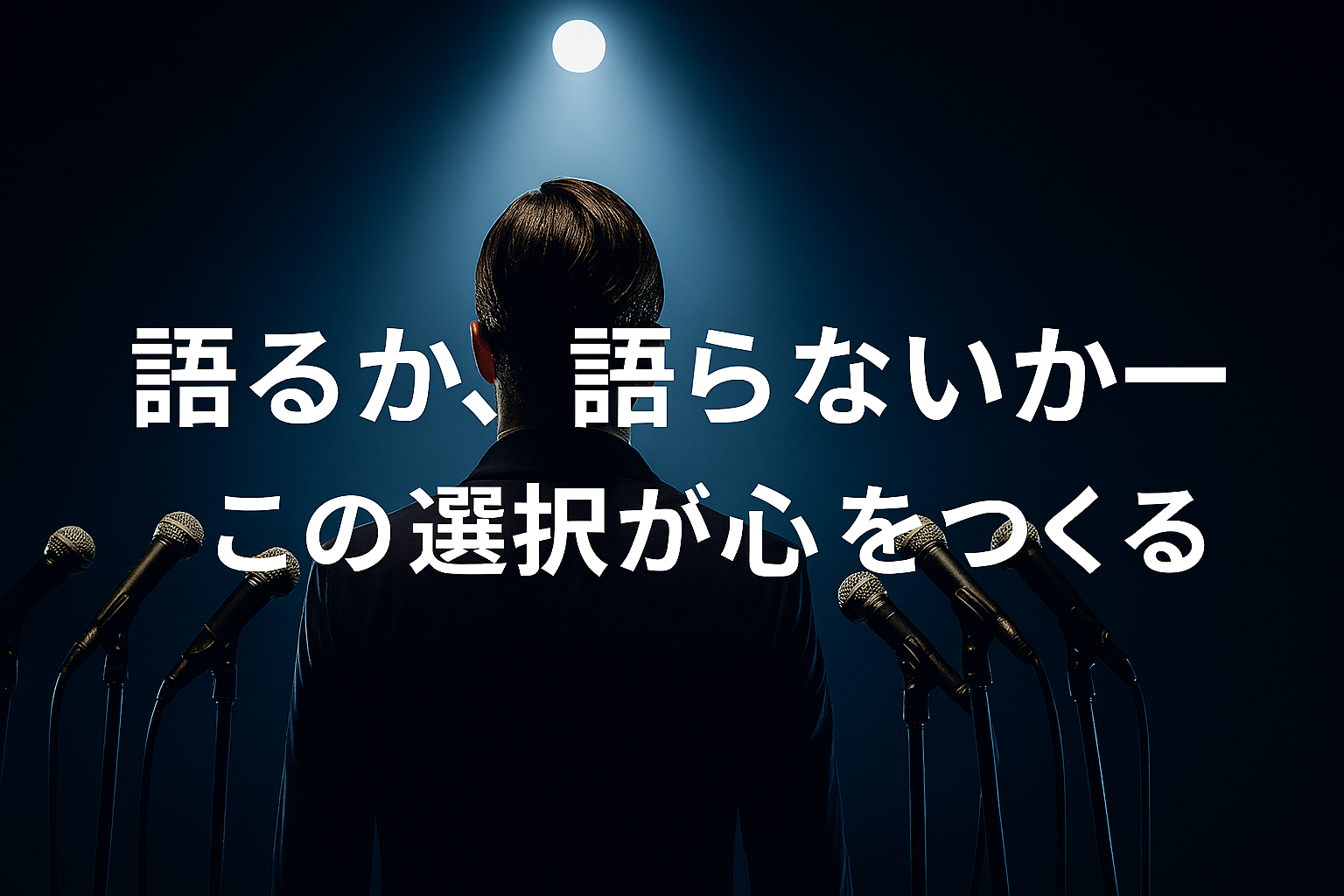
愚痴っても良いのか?──討論会から始まった問い
「愚痴ってもいいのか?」 この問いに、明確な答えを持っている人は少ないかもしれません。 私自身は、どちらかと言えば「愚痴は良くないもの」と思っていた一人です。
そんな中、毎月開催している一般社団法人日本スポーツメンタルコーチ協会の勉強会で、 今回のテーマが「愚痴」になった時、思わず身を乗り出しました。
この勉強会は、毎回一つのテーマに対してディベート形式で行われます。 「愚痴った方が良い」グループと「愚痴らない方が良い」グループに分かれて討論することで、 一つの視点ではなく、複数の角度から物事を見る力を養う場となっています。
私は「愚痴は良くない」グループに配置されました。 その立場から議論を進める中で、改めて愚痴の本質に向き合うことになったのです。
愚痴の定義
──言っても仕方のないことを嘆くこと
広辞苑によると、「愚痴」とは
つまり、解決の見込みがない不満や嘆きを口にすること。
一方で、「ぼやき」は
で他人に聞かせる意図は薄いとされています。
この定義を踏まえると、愚痴は「誰かに聞いてもらうことを前提とした不満の表現」であり、 その扱い方によって、メリットにもデメリットにもなり得ることが見えてきます。
愚痴のメリット
──“吐き出す”ことの効能
討論の中で挙げられた「愚痴のメリット」は、以下のようなものでした:
- ストレス緩和:我慢しすぎると、かえって心身に悪影響を及ぼす
- コミュニケーションの潤滑油:不満を共有することで、関係性が深まることもある
- スッキリする:誰かに聞いてもらうだけでなく、一人でぼやくことも効果的
- 仲間との結束力が高まる:同じ不満を持つ者同士が連帯感を持つ
実際、心理学でも「感情のラベリング(言語化)」はストレス軽減に効果があるとされています。 言葉にすることで、感情が整理され、脳の扁桃体の過剰な反応が抑えられるという研究もあります。
愚痴のデメリット
──“習慣化”のリスク
一方で、私が担当した「愚痴は良くない」側の意見には、以下のような懸念がありました。
- 相手の気分を損ねる:聞かされる側にとっては負担になることも
- 愚痴の対象に伝わるリスク:人間関係のトラブルにつながる可能性
- 一時的なスッキリ感のあとに残る嫌な気分
- 愚痴が習慣化すると、言わないと気が済まなくなる悪循環
- 自分の評価が下がる可能性:愚痴を聞いた人が第三者に伝えるリスク
- 脳への悪影響:脳は主語を認識できないため、他人への愚痴も“自分に言っている”と解釈する
- 他人軸になる可能性:自分の感情が、他人の言動に左右されるようになる
この「脳は主語を認識できない」という点は、神経科学の分野でも注目されています。 ネガティブな言葉を繰り返すことで、脳はそれを“自己への言葉”として処理し、 自己肯定感や意欲に影響を与える可能性があるのです。
愚痴の“扱い方”がすべてを決める
討論を通じて得た最大の気づきは、 愚痴には「良い・悪い」の二元論ではなく、「扱い方」がすべてを決めるということ。
誰に、どんなタイミングで、どんな言葉で伝えるか
目的は“発散”なのか、“共感”なのか、“解決”なのか
それによって、愚痴は「整える言葉」にも「濁らせる言葉」にもなる
つまり、愚痴は“言葉の使い方”次第で、メンタルの質を左右するのです。
選手の思い込みのフタを外すために
このような討論会を通じて、私自身が改めて感じたのは、 「物事を一辺倒で捉えない習慣」の大切さです。
選手の中には、「愚痴=弱さ」「不満=甘え」と思い込んでいる人もいます。 でも、そうした思い込みのフタを外すことで、 新しい景色が見えたり、心の余白が生まれたりすることがある。
だからこそ、私は選手に対しても「多角的な視点」を持ってもらえるような関わり方を意識しています。 そして、自分自身もその姿勢を忘れず、常に学び続ける存在でありたいと思っています。
成長の場に身を置くという選択
今回の討論会もそうですが、私は「少しでも成長できる可能性のある場」には、 できる限り足を運び、顔を出すようにしています。
それは、選手にとってより良いメンタル環境を整えるために、 まずは自分自身が柔軟で、深く、成長し続ける存在である必要があると感じているからです。
選手ファーストであること。 そのために、自分自身のアップデートを止めないこと。 それが、私のスポーツメンタルコーチとしての在り方です。
最後までお読み頂きありがとうございました。
コラム著者