頑張るは楽しむに勝てない──習慣化の鍵は“楽しむ力”にある
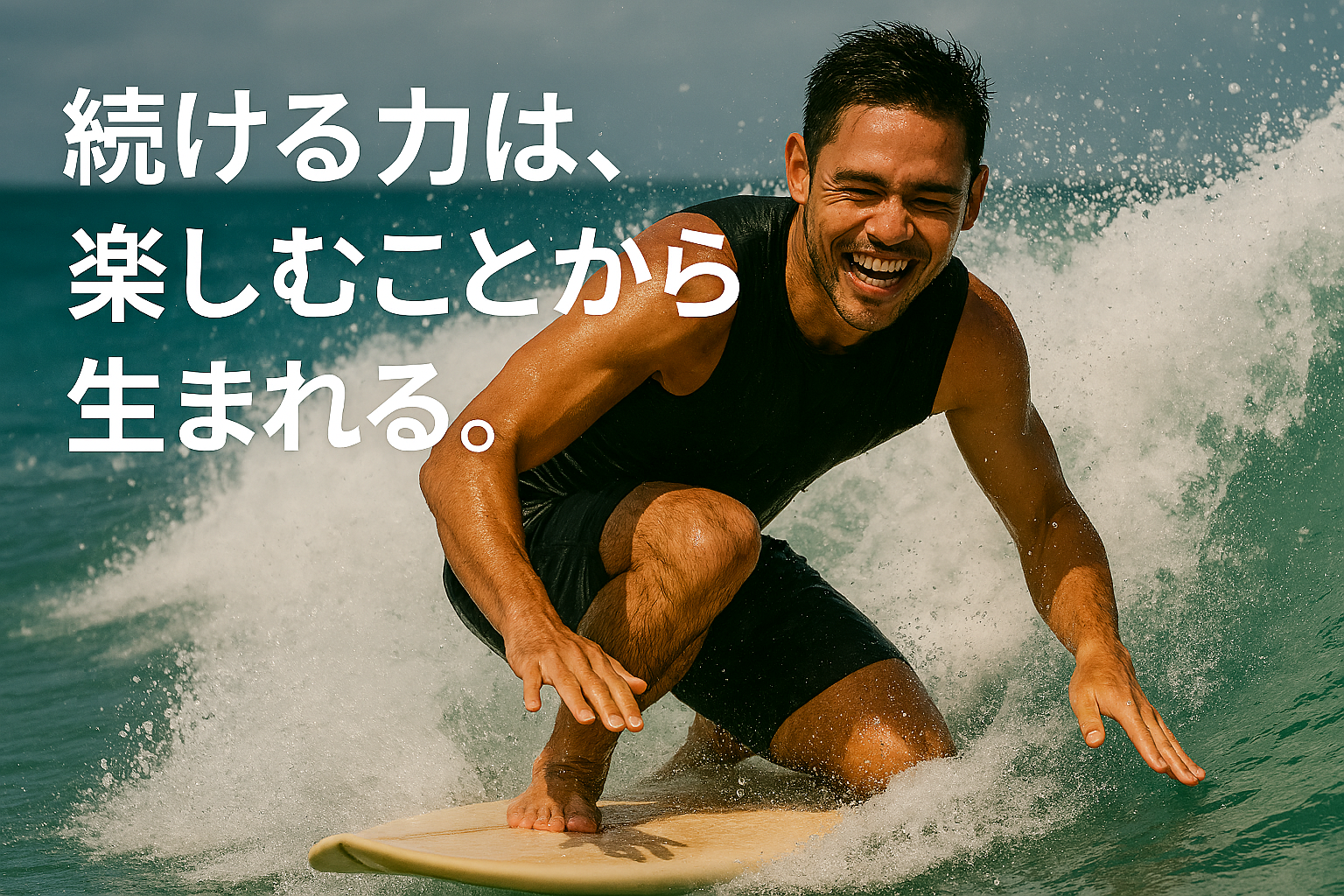
「頑張る」は美徳のように語られる。 努力、根性、継続──その言葉の響きは、どこか重く、真面目で、正しい。
でも、ふと立ち止まってみると、こんな問いが浮かぶ。 頑張ることは、本当に続ける力になるのか?
実は、習慣化の本質は「頑張る」ではなく、「楽しむ」にある。 そしてこの“楽しむ力”こそが、結果に囚われず、長く続けるための鍵になる。
頑張るは、いつか限界がくる
「頑張る」は、意志の力を使う。 目標に向かって努力することは素晴らしい。 でも、意志の力は有限だ。心理学ではこれを「意志力の枯渇(ego depletion)」と呼ぶ。
スタンフォード大学の研究では、意志力を使い続けると、判断力や集中力が低下することが示されている。 つまり、「頑張る」を続けるほど、心は疲弊していく。
そして結果が出なかったとき──
「こんなに頑張ったのに」と苦しくなり、 「別の方法はないか」と迷い始め、 「もう無理かもしれない」と諦めてしまう。これは、誰にでも起こりうる自然な反応だ。
楽しむことは脳を習慣化モードに切り替える
一方、「楽しいからやっている」ことには、意志力がいらない。 脳科学的には、楽しさを感じるとドーパミンが分泌され、行動へのモチベーションが自然に高まる。
ドーパミンは「報酬予測」に関わる神経伝達物質であり、 「これをやると気持ちいい」「またやりたい」と感じることで、行動が習慣化されていく。
つまり、「楽しいこと」は、脳が自動的に繰り返したくなるように設計されている。
アスリートの実話
──“楽しむ”が結果を生む
トップアスリートの多くは、「楽しむこと」を習慣の核にしている。
たとえば、陸上十種競技の選手である堀内隆仁氏は、走ることが苦手だった。 しかし彼は、LEDを使って腕の軌道を可視化するツールを自作し、 「自分の身体と対話する」ことを楽しみながらスキルを磨いていった。
彼の学びは、競技場だけでなく、日常の歩き方や立ち方にも及び、 「生活そのものが競技につながっている」という感覚を育てていった。
このように、楽しむことが“学びの感度”を高め、結果的に競技力向上につながっている。
習慣化の本質は「結果に囚われないこと」
「頑張る」は、結果を求める。 「楽しむ」は、過程を味わう。
この違いが、習慣化の成否を分ける。
結果を求めすぎると、出なかったときに心が折れる。 でも、楽しんでいるときは、結果が出なくても続けられる。 なぜなら、やっていること自体が報酬になっているから。
これは、私のコラムでも何度も出てきている心理学でいう「内発的動機づけ」の力だ。 外からの報酬ではなく、内側から湧き上がる動機が、行動を持続させる。
習慣を“楽しむ”に変えるためのヒント
では、どうすれば「楽しむ習慣」を作れるのか。
いくつかのヒントを紹介したい。
- 小さく始める:いきなり完璧を目指さず、まずは「できた」を積み重ねる。
- 記録する:自分の変化や気づきをメモすることで、楽しさが可視化される。
- 仲間と共有する:誰かと一緒に取り組むことで、楽しさが倍になる。
環境を整える:目につく場所にビジョンボードを貼るなど、視覚的な刺激を使う。
“やらなきゃ”を“やりたい”に変える言葉を使う:言葉の選び方が、感情を変える。
スポーツメンタルコーチは“楽しむ習慣”の伴走者
こうした習慣づくりを支える存在としても、スポーツメンタルコーチがいる。特に私上杉亮平は、目標達成のためだけでなく、 「楽しむことを軸にした習慣づくり」を大切にしている。
日常の中で「続けたいことがある」「自分を整えたい」と思う人にも、 メンタルコーチングは大きな力になる。
最後のメッセージ
──「続けたいのに、続かない」その揺らぎに寄り添う
もし今、 「頑張っているのに、うまくいかない」 「続けたいのに、気持ちがついてこない」 そんな揺らぎの中にいるとしたら──
それは、あなたが怠けているからでも、意志が弱いからでもありません。 ただ、今の“軸”が少しだけ、あなたの心とずれているだけかもしれません。
習慣は、根性でねじ伏せるものではなく、 心にそっと馴染ませていくもの。 そのためには、「楽しむこと」や「自分らしさ」が、何よりの土台になります。
誰かと一緒に整えていくことも、 自分のペースで見つめ直すことも、 どちらも大切な選択肢です。
もし、今の自分に少しでも違和感があるなら── その感覚を、どうか置き去りにしないでください。 それは、変化の入り口かもしれません。
そんな人こそまずは是非体験メンタルコーチングを受けてみるという選択肢を増やしてみてください。
必要なときに、必要な人と出会えるように。
そんな余白を、そっと残しておきます。
最後までお読み頂きありがとうございました。
コラム著者