モチベーションが高まる時こそ要注意|継続できない原因と心を守る思考法
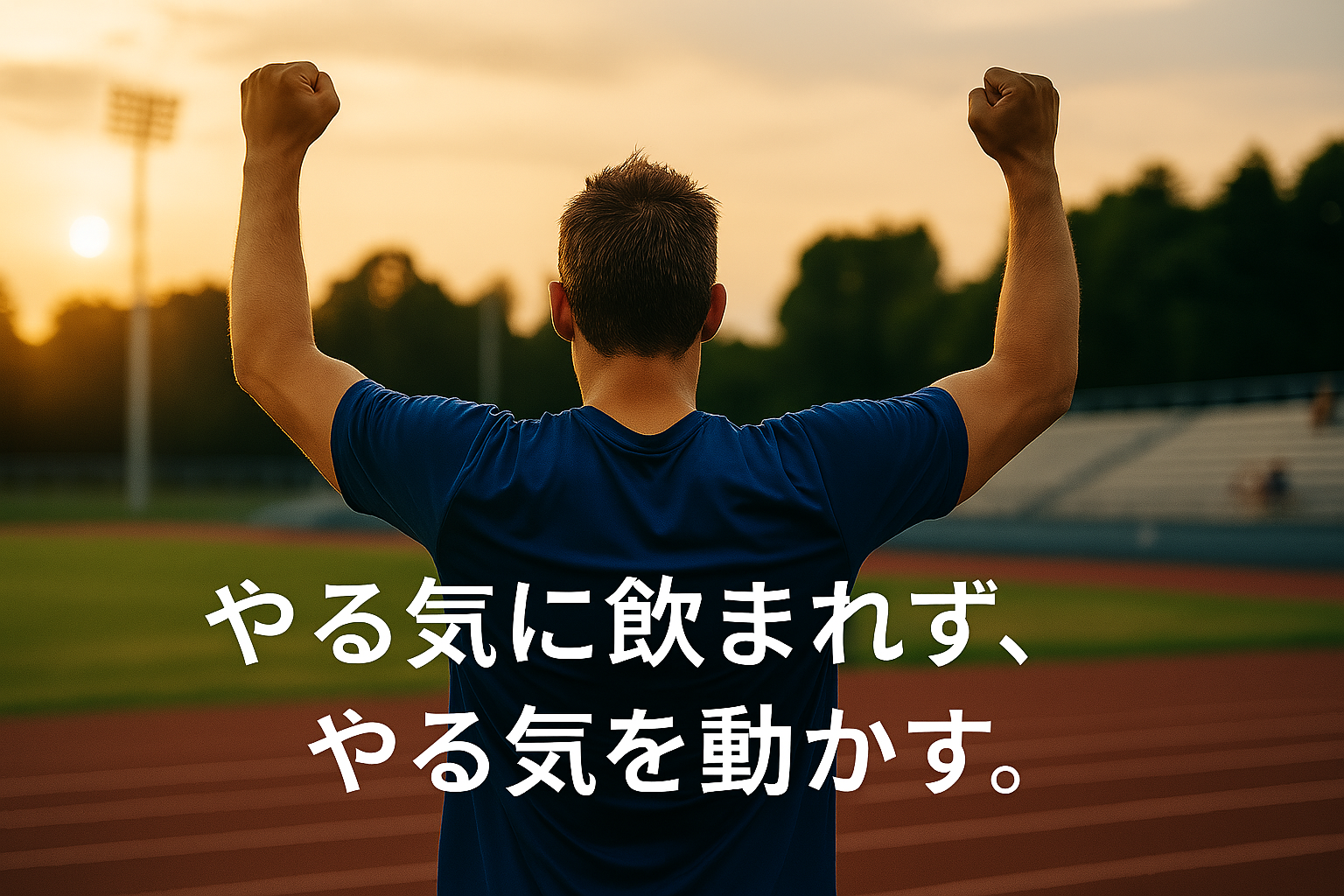
「よし、やってやるぞ」 「今ならいける気がする」 「この勢いで一気に変えよう」
そんな風にモチベーションが高まった時、人は驚くほどの行動力を見せる。 新しいチャレンジ、環境への飛び込み、習慣の改善──その瞬間は、まるで自分が変われるような気がする。
でも──その高まりは、時に“大きな反動”を生む準備段階であることを忘れてはいけない。 モチベーションが上がった時ほど、心理的なハードルは見えなくなり、 自分にとって適切なペースや領域を超えてしまいやすくなる。
このコラムでは、「モチベーションが高まっている時こそ危ない」という逆説的テーマを通して、 感情と継続の距離感をどう整えるかを紐解いていく。
モチベーションの高まりが生む2つの誤解
1. 高まっている=今すぐ大きく変えられる、という錯覚
人は感情が高まると、自分の能力まで拡張されているように錯覚する。 でも、モチベーションの高まりとはあくまで「エネルギーの源泉」であり、 「継続可能な能力」や「積み重ねの実績」ではない。
→ この錯覚のまま、一気にハードルを上げた挑戦をすると、 → 結果が出なかった時に“落差のショック”が返ってくる。
2. 今ならすぐに結果が出るはず、という期待
モチベーションが高い状態は、「目先の変化への期待値」が異常に上がっている状態。 → 今やればすぐ効果が出るはず → やれば必ず報われるはず
でも、変化は往々にして“遅れて”やってくる。 このタイムラグに耐えられず、心が折れてしまう。
高まったモチベーションの末路|よくある心理の流れ
- 高まり → 一気に行動開始(トレーニング・勉強・習慣改善など)
- 過剰な目標設定 → 現実との差に焦り
- 結果が出ない → 自責・否定的な自己評価
- モチベーションが下がる → 挫折・停滞
- 「やっぱり自分には無理かも」という自己解釈
→ こうして、せっかく芽生えた熱が“自分を否定する記憶”になってしまう。
実例|河村勇輝のマインドセットが教えてくれること
河村選手は、NBA挑戦の中で何度も評価や出場機会の壁にぶつかっている。 しかし、2025年シーズン終了後のインタビューではこう語った。
「気持ちよくない環境は必ず自分を成長させる」 「悔しさを味わうためにアメリカに来た」
試合での好プレーだけでなく、出場できなかった時間や評価が届かなかった瞬間を “意味ある時間”として認識する力こそが、彼の本質的な強さ。
つまり、「やる気があるとき=成果が出るべき」と考えるのではなく、 やる気があるときこそ“冷静に向き合うこと”が必要であるという視点が、大事になる。
モチベーションとの健全な付き合い方|3つの思考技術
1. 高まりは“行動の起点”であり、“成果の保証”ではない
→ モチベーションの波は使うもの。乗るのではなく、流れを整えるもの。
2. 目標は“興奮”より“持続”を基準に設計する
→ ハードルを上げるなら、「3日後に続けられるか?」を自分に問う。
3. 反動が来たときの“感情のクッション”を先に準備しておく
→ 「思ったより成果が出ないかもしれないけど、意味のあるプロセスではある」 → この考え方を事前に持っているだけで、落差が緩やかになる。
最後に──あなたの“熱”を消さないために
モチベーションが高まる瞬間は、確かに貴重で尊い。 でも、その熱に“振り回される”と、 いつか自分の感情に対してさえ、疑いを持つようになる。
だからこそ── 高まった時ほど、立ち止まる勇気を持ってほしい。 その熱を、最初の衝動で使い切らないために。 その熱を、自分の生き方に変えていくために。
熱は使い方次第で、ただの一過性にもなるし、 人生を変える力にもなる。
「やる気がある時こそ、丁寧に整える」──その感覚が、競技者としての真の強さにつながっていく。
コラム著者