一瞬の栄光ではなく“続ける力”を信じて―遠藤保仁に学ぶ競技者として生き残るという選択
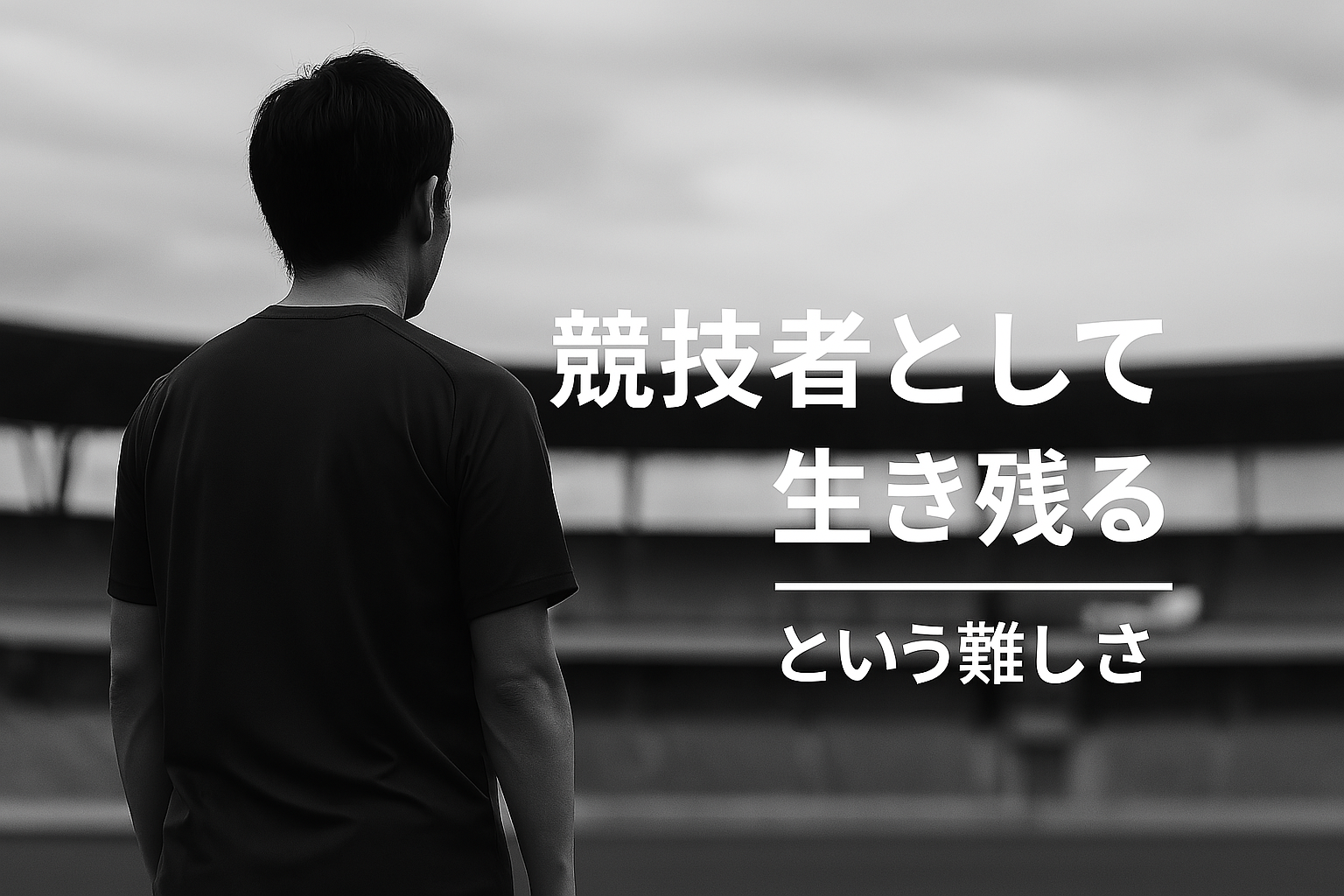
一瞬の輝きより、生き残ることの難しさ
「その場の栄光」ではなく、「競技者としての継続」を目指すすべての人へ
「勝った」「注目された」「称賛された」。 そんな一瞬の栄光が、アスリート人生の中に確かに存在する。 ただ、目を逸らしてはならないのは、その後。 栄光のあともなお、競技を続け、チームを支え、変化する身体や環境と向き合い続ける、“生き残る”というもう一つの競技である。
一瞬の輝きは、派手な光を放つ。 だからこそ、生き残り続けるということは、その光の裏で、誰に見られていなくても準備をやめないことが大切なのです。
一瞬の栄光と、“継続”という選択の重み
スポーツの世界では、「勝つ」ことが最も価値あるもののように語られがち。 もちろん、勝利は素晴らしい。ただ、それは単なる“結果”であり、キャリア全体から見れば一瞬の出来事にすぎない。
“続ける”という選択には、日々の地味な努力、揺らがない覚悟、変化への対応力、そして孤独と向き合う強さが必要になる。
「勝つこと」は記録されるが、「残ること」は人格をつくる。 そんな静かな強さこそ、競技者として最も尊いものかもしれない。
遠藤保仁─「輝ける才能」ではなく、「耐える準備」の象徴
遠藤保仁選手は“黄金世代”の一員として早くから注目を集めました。 しかしそのキャリアは、順風満帆ではなかった。
1999年ワールドユース。彼は当初、レギュラーどころかベンチ入りすら危うい立場だった。 稲本潤一選手の負傷で巡ってきたチャンスを掴み、全7試合にフル出場。
>「イナがケガしてなかったら、俺は多分出てない」
そう語る彼は、その後も長く第一線に立ち続け、 Jリーグ最多出場記録、日本代表歴代最多キャップ、アジア年間最優秀選手賞…… 気づけば、誰よりも長く、誰よりも安定して日本サッカーを支えてきた“継続の象徴”となっていました。
しかしその裏には、“輝く瞬間”をつかめるよう、「いつ自分の時代が来てもいいように準備し続けてきた」という地道な日々があった。
生き残るために必要なのは、才能より“見えない力”
遠藤選手はこう語る。
> 「サッカーに必要なのは、派手なテクニックじゃなくて、考える力と基本を徹底できること」
40歳を過ぎて戦い続けられた理由。 それは、基礎技術(止める・蹴る)を磨き続け、戦術眼や状況判断を強みに変えた“頭の使い方”にあった。
また、華やかな代表の舞台に選ばれながらも出場機会に恵まれなかった2006年W杯後には、 「球際が弱い」自分を変えるべく、体幹・筋力・メンタルを徹底的に鍛え直した。
「負けたことでしか気づけないことがある」。 そう信じて、変化を恐れず、積み重ねを止めなかったのです。
メンタルの視点から見る“生き残る力”
生き残る競技者に共通するもの──それは、“続けるためのメンタル”です。
- 自己効力感を保つ力
小さな成功を重ね、「自分はできる」と感じられる環境を自分でつくる
- 成長志向に切り替える力
批判や不調を受け止めながらも、「どう改善できるか」と問い直す思考力
- ストレスを流す技術
遠藤選手の言葉「終わったことは考えてもムダ」のように、感情の引きずりを最小限にとどめる
- 自分で選ぶという感覚(自律性)
周囲の評価ではなく、「自分で選んでやっている」という軸を持ち続ける
- 柔軟に変化を受け入れる心
若い頃のように攻撃を担うだけでなく、年齢に応じて役割を変えながら価値を発揮し続ける勇気
これらはすべて、一瞬の活躍ではなく「長く競技を続ける」ために必要な土台なのです。
最後のメッセージ
一瞬の栄光、輝きは、誰かの記憶に残るかもしれない。ただ、生き残り続けた人の姿勢は、誰かの人生を変える。
「その瞬間の栄光」ではなく、「自分の時代が来たときにちゃんと受け取れる準備をしてきたかどうか」。遠藤保仁という人は、その問いに“はい”と言える人生を歩んできたのだと思います。
だからこそ、今を生きるアスリートたちに伝えたい。 “その瞬間”のためだけに燃え尽きるのではなく、“生き残る”ことに賭けてほしい。
それは、目立たなくても、すぐに評価されなくても、静かに光を放ち続ける、真に価値ある競技人生を育てていく選択なのだから。
コラム著者